古典イタリア歌曲を数曲終え、発声もイタリア語も少し慣れてきた方の、今日はとても有名なCaro mio benのレッスンです。
発声なしでいきなり歌ってもらいました。最初からとても良い演奏でしたが、イタリア語の発音ミスが少しありましたので修正しました。とても勘の良い方ですぐに修正できました。
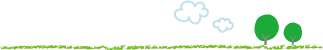
ここでこの曲のちょっとした説明。ごく普通のメロディーは、出しやすい中間域の音程から始まり、徐々に高くなりピークを迎えて、また最初の音に近いところまで下がって終わるものが圧倒的に多いです。今まで歌った曲で例を紹介しました。しかしこの曲の始まりはピークから始まります。通常のメロディーの前半がないような感じです。恋人への愛を歌う曲ですが、想いの強さがあふれ出るような曲の始まりになります。冒頭はpの指示がありますが、強い感情が歌われなければいけません。
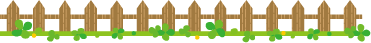
もう一度冒頭を歌って頂きました。冒頭のPの指示に縛られず、しかし乱暴でもない表現になりました。ここで私は横隔膜の動きを見ます。(見ると言ってもほとんど音で判断します)うまく歌えるようになると正しい横隔膜の動きになります。良い動きにならないようであれば、発声練習に一時切り替えて横隔膜を刺激していきます。
横隔膜と曲の表現に関連性が出てきたら、どんどん音楽的な歌になるように音楽を動かしていきます。場合によっては曲のテンポを少し動かしたり、強弱を自然に変えるようにレッスンを進めていくと、横隔膜の動きが自然になってきた人の歌はどんどんといきいきとしたものになっていきます。
私がピアノを弾いているときには伴奏のテンポや強さを少し変化させるし、場合によっては少し体を動かしながら弾いたりします。ピアニストが来てくれているときには目の前で指揮しながら動かしていきます。私のレッスンに来てくれているピアニストは皆さんレッスンの意図をくみ取って音楽を動かしてくれていて、大変助かっています。

横隔膜と表情のつながりが出てくればこの日のレッスンは大成功です。この連動が非常にうまく出来るようであれば、次回横隔膜に集中した発声レッスンから入り、横隔膜の運動の自覚を目指します。うっすらと連動が見られるようでしたら、同じ曲または新しい曲でもう一度練習します。
全く連動が起きないことはまれですが、その時は別の角度からのレッスンに切り替えます。

コロナの影響で練習できない方へ

イタリア古典歌曲~初歩のレッスンで一番良く使われる楽譜

声楽指導者の頭の中を少し公開1 ~レッスンの組み立て方

少し高度な音程練習(和音)

はじめに~レッスンで

横隔膜の自覚~強くよりも自覚が大切

喉を開ける練習の1例

歌が苦手だと思っている方へ

メゾソプラノのレッスン~胸声について

始めての方~体験レッスンで
カテゴリー一覧
 久米音楽工房 声楽、発声、ピアノのレッスン 神奈川県川崎市
久米音楽工房 声楽、発声、ピアノのレッスン 神奈川県川崎市 



