パッサージョを超えて高い音の練習をするときに、ジラーレさせるとか、アクートの声とか分かるような分からないような用語が並ぶことがあります。その時々に声帯はどうなるのかを説明していきます。

特別な用語を使わないと表現できないこともありますが、分かりにくくなったり、本来の意味とは違う捉えられ方をすることもあり、あまり多用するのはどうかとも思います。レッスンでは分からないものはすべて説明しますので、いつでも聞いてくださいと伝えています。
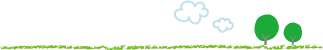
高い音を出すときに、「かぶせる」「曲げる」といった表現がされます。イタリアではGirare(ジラーレー回す)ドイツではDecken(デッケンー覆う)といわれます。なんとなく共通したイメージが感じられます。なぜこの曲げるとかかぶせるとかが必要なのでしょうか?
高い音を出すためには、声帯が徐々に薄く引き延ばされなければなりません。声帯は気管の中にあり、前は閉じていて後ろは開閉できるようになっています。この声帯を前後に引っ張ることが声帯が薄く引き延ばされることになりそうですが、そのときに声帯の前が下に下がるように引っ張られていきます。発声の仕組みで図解していますので、参考にしてください。つまり声帯は前下、後上の方向に引っ張られますので、高い音に向かって声帯は立ってくるように感じられるのです。結果顔をやや下を向くような方向に傾けることになります。この運動を『回す』『かぶせる』『覆う』と表現するのです。
発声の時に手をつける人が多いのですが、一番多い形に、耳の周りを手が一周するような形、耳の下から耳の後を通って、さらに耳の上から前に向かっての動きです。これがジラーレの感覚です。
高い音に向かってチェンジさせるのと全く同じです。チェンジが上手くいかず、高い音が薄い音になっていない時にはジラーレが必要になります。
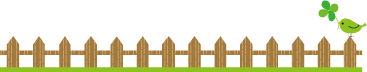
ジラーレがうまくできるようになると高い音が少し出しやすくなりますが、この声帯の進展運動のみが働いて高音のための準備は整ったとしても、音質が薄く、ファルセットに近いものになり、力強さは出てきません。つまり声帯の閉鎖が足りないのです。そこでアクートが必要になってきます。十分に伸ばされた声帯の中央部分がしっかりと閉鎖されると、とても明るい鋭い音が出てきます。これがアクートといわれる音です。
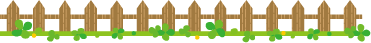
ネット上ではベルカントはジラーレで歌い、現代はそうではなくアクートで歌うとか、女性はジラーレで歌うが、男性はアクートで歌うといったものがありましたが、残念ながら違うでしょう。もしそうだとするとベルカントの高音は常に声帯にやや隙間のあるファルセットのような音で、その音がだめなわけではありませんが、それだけしか使えないとしたら、高音でフォルテは出ません。未完成な発声法だということになります。逆にすべて高音をアクートで歌うとすればフォルテしかありませんので、デクレッシェンドはないことになります。これも未完成な発声法です。高音は十分に引き伸ばされた声帯が準備されたまま、自在に閉鎖の強さを変化させられるのが目標とする声です。ジラーレで歌った方が良いとかアクートで歌った方が良いといったようなものではありません。全く別の運動だということです。
カテゴリー一覧




