発声において必要とされることは多岐にわたります。呼吸や共鳴、姿勢など、「こうでなければならない」「こうであってはいけない」といった指導がなされることがよくありますが、これらはしばしばもっともらしく聞こえますが、漠然としていて頼りない方法に終わってしまうことが多いです。その結果、頭や体が混乱してしまうという経験は、少なくないのではないでしょうか。
しかし、声を作り出しているのは間違いなく声帯です。したがって、声帯の運動を抜きにして呼吸や姿勢について語ると、それは誤った理解を招く危険があります。呼吸や姿勢は、発声において声帯の動きにどのように影響を与えるかという視点で捉えたとき、初めてその重要性が明らかになります。

お腹や姿勢を気にしすぎて声を聞いていないこともよくあります。
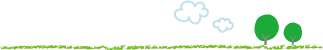
さて本題ですが、頭声、胸声といった声区が発声では良く話題に上りますが、これは声帯の基本的な状態の違いによる音質の差です。本当によい頭声や胸声という話は別のところで考えるとして、少し大まかな表現になってしまいますが、頭声では声帯を薄く引き伸ばす力(甲状輪状筋等の伸展筋)が強く働き、胸声では声帯を厚く強く触れ合わせる力(声帯筋)が働きます。よって頭声では細い弦を振動させるように、高い声が出しやすくなりますが、それだけでは細い弱い音になってしまいます。一方胸声では高い声が出しづらく、しかし太い大きな声が出ます。(厳密にはその他の筋肉も関係し合って、音質が変わりますが、ここでは簡単に話をさせて頂きます。)
そして実際は頭声であっても胸声的なものが混ざり、胸声であっても頭声的なものが混ざることにより、バランスが取れ、自然に音量や音程,音質を変化させられるようになります。さらに、頭声から胸声へ、また逆にも自然に移行できます。声区に関してはこちらもご参照ください。
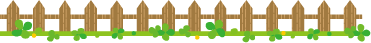
少し難しい話になりますが、ここで一つ重要な点があります。それは、発声に関わる筋肉は別々の筋肉であり、互いに影響を及ぼし合いながらも、ある程度は独立して動くということです。良い声を作るための条件としては、これらの筋肉が常に協調して働き、自由にその働きの強さを調整できる柔軟性を持つこと、または反対の筋肉が強く働いても他の要素が崩れることなく安定していることが挙げられます。

声帯は常にある程度引き伸ばされていないといけません(喉を開く)。しかし、この引き伸ばし筋と声帯の厚さを変える筋肉(声帯筋)は独立して使えますので、声帯を厚くしたまましっかり引き伸ばすことも可能です。低い良い音はこの状態で出来ますし、とても力強い高音も同じ声帯の状態で作られます。
カテゴリー一覧






