前回調の判断の仕方について書きました。さて、何調か分かったところでそれだけでは音楽の理解には何もつながりません。そこで調性格論について少し考えてみます。例えばハ長調はシンプルな素朴な感じといった、調性が持っている独特なイメージのようなものです。
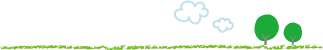
マッテゾンやシューバルトの調性論が有名ですが、少し例を挙げてみます。主にこの2人を混ぜて書いてみます。
ハ長調・・荒削りで大胆、単純、素朴
ヘ長調(♭1つ)・・寛大、沈着、愛、徳、平和、単純素朴、牧歌的
ト長調(♯1つ)・・輝き、真面目、活発、若人の調、誠意
ハ短調(♭3つ)・・並外れて愛らしい、哀しい、柔和の中に真剣な情熱を持つ悲劇的な力
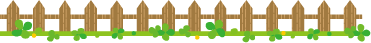
ほんの1例ですが、すべての調に渡ってこのようなイメージが書かれています。共感するところもあり、そうでないところもあるといった感じではないでしょうか。このように本に書かれた調性のイメージに縛られるのはあまりおすすめできませんが、確かに納得いくものもたくさんあります。ハ長調の単純な素朴な感じ(バッハの平均律曲集の1曲目など)、ト長調の明るく誠実な感じ(魔笛のパパゲーノの調)、ヘ長調の平和な愛に満ちた感じ(シューマンのトロイメライなど)。

ここで2つの問題を考えてみたいと思います。調律の際の基準音は段々高くなってきました。バッハの頃とでは半音ほど高くなっていると言われています。例えばバッハのト長調の曲を今の楽器で演奏すると、バッハの頃の調律では変イ長調の曲になってしまう。調性論が確かだとすると、同じ曲の性格が変わってしまうことになります。
次に歌曲などは声の高さに合わせて移調して歌われます。移調してしまうと本来の音楽の持つ性格が変わってしまい、出来ることならば移調しない方が良いという事になるのでしょうか?
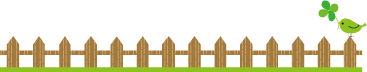
調性論を考える時に、平均律と純正律といった調律の差を云う人もいますが、あまり賛同できません。調律をするときに1オクターブの音の関係は簡単です。例えば今は中央のラの音を440Hz位で調律しますが、その1オクターブ上は完全に2倍の周波数880Hzになります。これだと1オクターブの関係の音だけになってしまいますので、調律は5度上の音を基準に作っていきます。5度上の音もきれいに溶けあった音になりますので調律可能です。(周波数が単純な整数比になるときれいに溶け合った響きになります。5度は2:3です) 例えばドの音を決めます。そして5度上のソの音を合わせます。さらに5度上のレの音を合わせます。1オクターブは何の問題もなく合わせられるので、1オクターブ下のレの音も合わせます。次はラの音、次はミ、次はシ、次はファ♯と言う風に進めていくと、12の音すべてを合わせられて、最後に元のドの音に戻ってきます。何の問題もなさそうですが、実は戻った時にほんの少し最初のドの音より高くなってしまうのです。これが調律を難しくさせていくことになるのです。
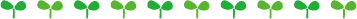
この調律(純正律)ではドを基準に作った場合ハ長調の和音はきれいに響きますが、違う調に転調した時に音のゆがみが大きくなり、転調に上手く対応してくれないことになります。そこでこのゆがみを極力少なくして、12の音の幅を均等に調律する平均律が開発されていくことになるのです。平均律では半音上の音の周波数は下の音の約1.05946・・・倍になるそうです。つまり440Hzのラの音の5度上のミは純正律では660Hz、平均律では659.25508・・・Hzになります。このずれから調性が変わると音楽の性質が変わる。とすれば、調性論は平均律の無かった過去の話で、 現代には全く意味のないものという事になります。
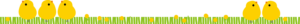
これは私のイメージなのですが、調の性格には音の絶対的な高さは関係なく、他の調からの関係性のみで作られたのではないかと思っています。例えばピアノを前にして、音の状態を調べる時にハ長調のスケールを最初によく弾きます。響きはどうかとか、音ムラはないかとか、何の表情も持たずにシンプルに音を聴くのにハ長調を弾いています。このシンプルさ、これから始まる感じがハ長調で、そのままファだけシャープを付けるとト長調になります。明るさが増し積極的な感じになります。これがト長調の感じ。またハ長調に戻ってこんどはシのフラットだけ付けます。明るさはあるものの穏やかな平和な感じになります。これがヘ長調です。またハ長調に戻り、こんどは♭を3つ付け短調にします。ハ長調のシンプルさとの対比からか深刻な運命を背負ったような逃れられないような重圧を感じます。ハ短調です。同じ♭3つでシのナチュラルをなしにするとほっとした優しさを持った明るさになります。同じ調号の長調(平行調)変ホ長調です。

このように調の性格は出てくるのではないでしょうか。元々のピアノがたとえ半音低く調律してあったとしても、すぐに耳は馴染んでその調律でハ長調、ト長調と感じていくのではないかと思います。今でこそほぼ同じ音で調律されますが、隣の教会のオルガンは違う調律がされていた時代なら、なおのこと絶対的な音の高さは重要では無かったのではないでしょうか。
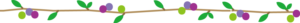
と言うことで現代の楽器で半音高く演奏されるバッハのロ短調ミサはハ短調に変わるのではなく、ロ短調ミサだし、移調して歌っても性格は元の調のままなので、無理して原調で歌う必要はないと思います。オペラなどではアリアを1曲音を下げると前後の音楽のつながりがなくなります。全部の音楽を下げる必要が出てきて、そのために困る人も出てくるでしょうし、とにかくすべての楽譜を書き換えなければなりません。結局頑張って原調で歌う必要があります。リサイタル等でアリアだけ歌う場合は移調もあり得るかもしれません。

ちなみにシューベルトの「竪琴弾きの歌」は3曲からなる歌曲集です。通常歌曲集を作る時は調に変化を付けます。例えば悲劇的なハ短調から始まり、フラットが1つなくなり悲しみがより深くト短調、そのままの調号で長調になり穏やかな変ロ長調、のようにすると劇の進行が感じられます。しかしこの「竪琴弾き」ではすべてがイ短調(amoll)です。シューベルトにとってこのイ短調は孤独の象徴だと思われます。彼にとっての孤独が1曲目で表され、その痛みや苦しみが2曲目にかかれ、それから永遠に解放されることもない彼の今、もしくは未来が3曲目にかかれています。同じ調にすることにより、竪琴弾きの解放されることのない孤独を描き続けることになります。調性の持つ性格の話でした。
カテゴリー一覧
 久米音楽工房 声楽、発声、ピアノのレッスン 神奈川県川崎市
久米音楽工房 声楽、発声、ピアノのレッスン 神奈川県川崎市



