「トスカ」で歌われる有名なアリアで、テノールなら是非一度は歌いたいと思うアリアではないでしょうか?テノールにとっては高音がとても大きな壁になりますが、この曲は最高音がA(ラ)なので、割と楽に歌えるのではないでしょうか?オペラのストーリーやこのアリアの意味などは、とても詳しく解説して下さっているサイトも多数ありますので、ここでは省略して、この曲の音楽的な側面を見ていこうと思います。
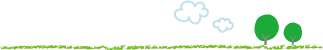
全体は32小節で、そのうちの15小節がレチタティーヴォ、残りがアリアで、演奏会でも、必ずレチタティーヴォとアリアセットで歌われます。23小節めから高い音が続きますので、この辺から最後に向かって難しいと感じることも多いかと思いますが、このことも今回は触れずに音楽のみを見ていきます。
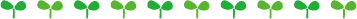
高音の大変さを抜きにすれば、この曲の難しさは別のことに表れます。テンポが分かりにくい、一定のテンポで歌うと面白くないし、下手に揺らすと壊れてしまいます。つまり音楽的なまとまりが作りにくい点です。まずレチタティーヴォでは、同じ音程で、言葉の抑揚に合わせた最小限のリズムの変化のみのフレーズが6回出てきて終わります。(3回目のみ和音の変化に合わせて2度上行します) 歌と言うよりしゃべりのシーンでレチタティーヴォらしいとも言えるかもしれません。
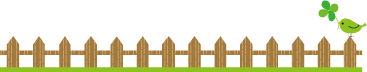
さていよいよ16小節目からアリアです。普通語りから歌に変わる時には何が起こるでしょう。 歌らしく聞こえるためには伴奏に同じようなリズムや似た音形の繰り返しが必要になります。 しかし、ここでは弦楽器が完全に歌のパートと同じ演奏をするだけの伴奏なので、テンポを決めたり方向性を作ってくれるパートが全く出てきません。そしてやっと伴奏らしいものが出てくるのが23小節目で、そこまではずーっとレチタティーヴォが続いているようにも感じられます。刻んでいるパートが無いので音楽は少し揺れていないと面白くないのですが、自由に揺らそうとすると、まとまりがなくなってしまいます。せっかく高音が出せるようになっても短いアリアなのに、こう歌うと良いと言った確信が持てない難しさがあります。しかしこのことがこの曲の一番の特徴なので、この部分と向かい合わないとこの曲は歌えません。

では音楽的はこの曲の構造を見てみます。伴奏らしいものが出てくるのが23小節めです。伴奏はずっと裏拍を演奏し続けます。ビオラから始まりファゴット、クラリネットと楽器が増えていきます。しかしこの形はここで初めて出てきたのではなく、最初から何度も出てきていました。レチタティーヴォ冒頭のクラリネットソロの後2小節目から1小節に1回だけの裏拍の伴奏があり、4小節めには2回、5小節目歌が加わると1小節通して裏拍の伴奏が出てきます。その後6小節目のクラリネットソロでまた途切れますが、その後は6小節間裏拍の伴奏は続きます。
こう見ていくと実はレチタティーヴォの方がより歌に近い伴奏があり、アリアになると途端に歌を思わせる伴奏が長々と出てこないことが分かります。この曖昧さが一つの特徴なのです。それぞれの特徴が明確ではないと音楽にならないわけではありません。そのままこの状況を歌にすれば良いのです。レチタティーヴォは歌っている間中、裏拍の伴奏が続きますので、これを壊さないテンポの安定感が必要です。それ以外は分かりやすく、音が上行しCis(ド♯)でピークを迎え、その後最初の音Fis(ファ♯)まで下がっていきますので、それに合わせた緊張感の推移を感じていきます。

アリアに入ってからもこの裏拍の伴奏は断片的に出てきます。この伴奏が出てくる小節は安定したリズムがいつも聞こえるようにします。つまり、16小節目は自由に遅く歌ったり、ある音を引き伸ばしても全く問題はありません。しかし、17,18小節目には1回だけですが、裏拍の伴奏が出てきます。ここは安定したテンポが聞こえる必要があります。16小節目のテンポを自由に揺らしたので、次の小節も揺らそうとするとまとまりがなくなり、プッチーニがせっかくこのまとまりのなくなりそうな音楽を、最小限の繰り返しだけでまとまりのある音楽に仕上げた技術が無駄になっていしまいます。
最初からレチタティーヴォとアリアという風に分類して書いてきましたが、全体を通して意味のある作り方をされているので、すべてを含めてアリアと言っても何の問題もありません。分類自体には意味は無いのです。レチタティーヴォとアリアだと、時間の都合でレチタティーヴォは省略することもありますが、この曲は省略してはいけません。
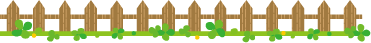
これだけでも締まりの無かった演奏が、しっかりとした演奏になります。それでもまだ迷うところが裏拍の伴奏のないところ、とりわけ16小節目と21小節目だと思います。特に楽譜の見た目が8分音符と16分音符のrit.付き。違うように演奏すべき感じもあるし、8分音符と、遅くなった16分音符にどのくらいの差があるのだろうと考えても良い答えは出てきません。このような部分は音符の見た目で変化を付けようと頑張る必要は無く、詩を感じるだけで充分です。最初は彼女との口づけをうっとりと思い出します。次は永遠の別れの苦しみを歌います。それだけです。このような部分に安定してリズムやテンポ感を入れたくなかったので、プッチーニはリズム伴奏を無くしたのです。
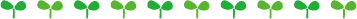
ここまでほぼ伴奏のリズムのみで考えてきました。音の高さからの考察を最後に少し加えておきます。h moll(ロ短調)です。ロ短調を一番はっきりさせるのはラ♯からシへの動きです。(調性に関しては他で書いていますので、詳しいことは他の項目を参考にして下さい。)しかしこの曲は極端にこのラ♯が少ない。最初に出てくるのが11小節目ですが、残念ながらシの音に解決してくれません。最初の解決は14小節めから15小節目にかけてです。その後もラ♯はなかなか出てこず、26小節目で出てきますが、残念ながらシの音に解決せず、29小節目から30小節目まで待たなくてはなりません。全曲を通して調性がはっきりするこの解決の音が2回しか出てこないのです。調性をはっきりさせないためにはもう一つ別の方法もあって、別の調にも見えるように作曲することもあります。例えば長調か短調かがはっきりしないとか、短調なんだろうけどホ短調とか嬰ヘ短調にも見えてしまうとか、も考えられますし、そのように作曲される曲もありますが、この曲は明らかにロ短調で、それ以外はあり得ないのに解決の音がはっきりしない音楽になっています。
何調か分からない音楽は気持ちが決まっていない証拠でもあります。絶望の中でも希望があるのかもしれないと感じたり、その絶望が悲しみになったり、怒りになったり、苦しみになったり、はっきりとはしていないが気持ちが揺れている時には調性も揺れていきます。この曲では気持ちは揺れていません。しかしながら非常に不安定なまま解決せずに進んでいきます。さらに全曲を通して転調がありません。ほんの少し12,13小節目で平行短調のイ短調の和音が使われますが、すぐに最初のはっきりとしたロ短調の動きである14,15小節目に向かいます。初めての解決の直前だけ少しロ短調を離れるように感じさせるのも上手いですね。テクニックの話だけになると感情的なものと結びつかなくなってしまうかもしれませんが、苦しいロ短調から少し離れて短調ではあっても違う世界に移行しようとしたのに、強引にまた苦しみのロ短調に引き戻されてしまうと言ったら、少し感情と結びつくでしょうか。
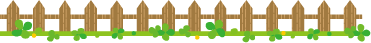
ちなみに冒頭のクラリネットソロのメロディー(何度も出てくるオペラ全体の象徴的なものです)が最後のファ♯をラ♯に変えるだけで、調性の安定感は増します。しかし全体の不安感が緩んでしまいます。たった1音でも作曲家は考えて考えて書いていますし、そういった音楽だから素晴らしいのでしょうね。雰囲気だけでメロディーを作っているのではないのです。
カテゴリー一覧
 久米音楽工房 声楽、発声、ピアノのレッスン 神奈川県川崎市
久米音楽工房 声楽、発声、ピアノのレッスン 神奈川県川崎市


